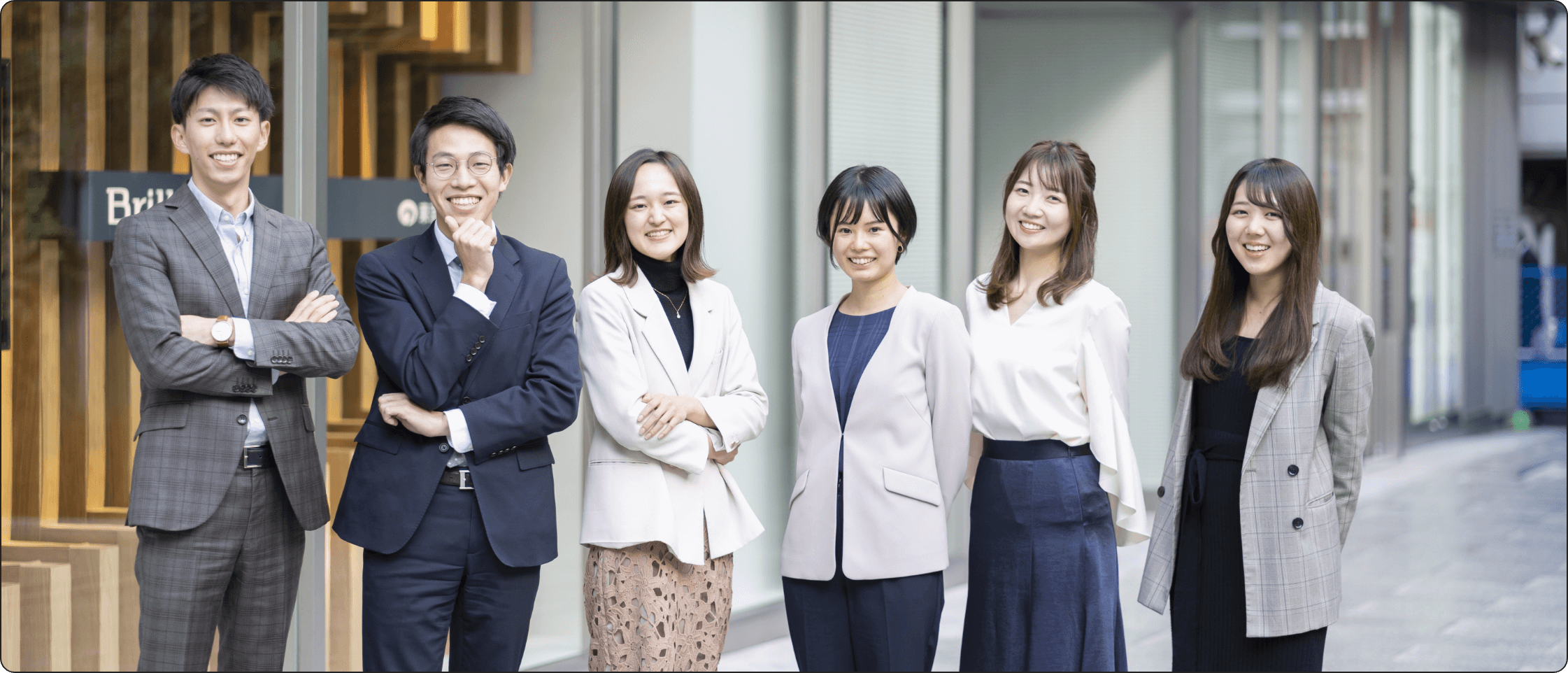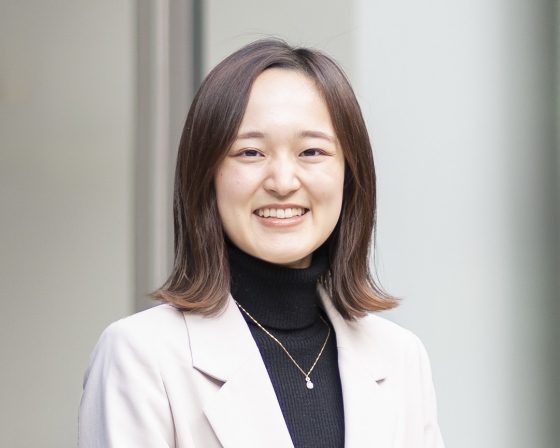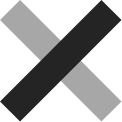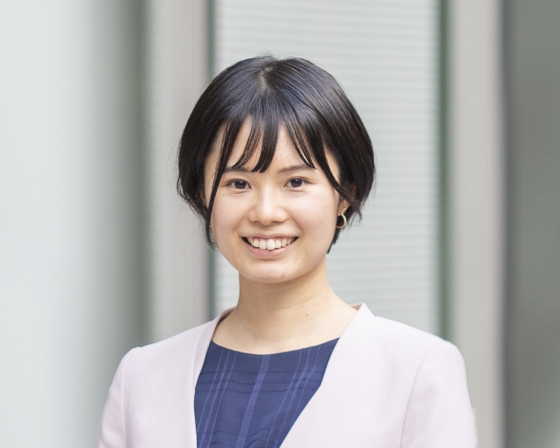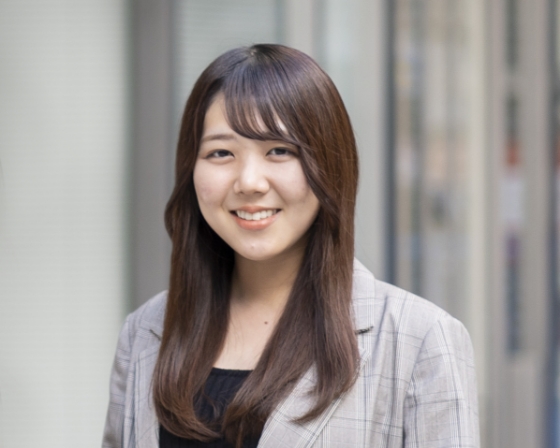CROSS TALK
QUESTION 01
「カウンセラー制度」が新入社員をサポート ビジネスパーソンとして成長の第一歩を支える
「カウンセラー制度」が 新入社員をサポート ビジネスパーソンとして 成長の第一歩を支える
伊藤
当社には、入社後1年間にわたって、新入社員1人に対して先輩社員が1人つき、実務だけでなくいろいろと相談できる「カウンセラー制度」があります。僕がカウンセラーを務めたのは城戸君で3人目。この制度、率直にどう感じたかな?
城戸
出会う前から、伊藤さんとはLINEのやり取りをさせてもらっていたので、最初から親しみやすい先輩という感じで。僕は言いたいことは言うタイプだったので(笑)、いろいろな場面で空気をつくってフォローしてもらいました。
伊藤
うん、城戸君は我が強いタイプ(笑)。でも、それを抑えることはしなかったね。すくすく伸び伸びと育ってほしいと思っているから。僕と城戸君のように、今日は当時のカウンセラーと新入社員の3組のコンビが集まったわけだけど、前川さんは、入社3年目でカウンセラーを務めたんですよね?
前川
そうなんです。自分に務まるのかどうか不安でしたね。カウンセラーはもう少し年次を重ねた人が務めるケースが多いですから。まずは牧野さんの良き相談相手になる、そんなスタンスで臨みました。何が起こっても手厚くフォローしたいと思っていましたが、牧野さんは優秀だったので、大事は起こりませんでした(笑)。
牧野
前川さんと年次が近いことが私にとっては嬉しかったですし、安心感もありました。困った時に本当に頼れる先輩でした。入社1年目の不安を払拭できたのも前川さんの存在が大きいですし、前川さんがいてくれたから失敗を怖れずに挑戦できましたね。
伊藤
阿部さんは初めてのカウンセラーだったけど、どんなことを心掛けていましたか?
阿部
カウンセラーの基本は実務を教えることですが、私自身が異動して間もないタイミングだったので、実務面では高橋さんと同じスタートライン。でも先輩として、人に納得して協力してもらうための丁寧なコミュニケーションや、社内人脈を活用することの大切さなどを伝えました。それから、「〇〇しなければならない」と言うのではなく、高橋さんの「〇〇したい」を後押ししていましたね。
高橋
阿部さんは新入社員の私から見て、とにかく仕事ができる人で圧倒されました。「できる人」とはこういう方なんだろうと思い、阿部さんの仕事ぶりをみて実務のみならず、ビジネスパーソンの基本的な考え方やあり方などを吸収していきました。
阿部
いやいや、そんなに褒めても何も出ないよ(笑)。でも、私たちも新入社員だった頃はカウンセラーがいたわけですが、会社や社員の中に溶け込む入口、ハブ的な役割を担ってくれていましたね。
伊藤
僕のカウンセラーはけっこう厳しい人で (笑)。身近にゴール地点を設けて、それをクリアしていくような指導を受けていました。私にとってはカッコいいビジネスパーソンであり、憧れに近い存在。なりたい姿であり、今の自分の姿とカウンセラーとのギャップを埋めていく姿勢が、成長に繋がっていると思います。
CROSS TALK
QUESTION 02
若手に任せる、挑戦させる それが東京建物のDNA
阿部
具体的な仕事を通じて、若手の成長をどのように支援しているのかにフォーカスしてみたいと思います。伊藤さんと城戸さんは、商業施設の用地取得を担当されていますね。
城戸
はい。まずは不動産仲介業者や不動産所有者の元を訪問し物件情報を取得。その土地の事業性を検証し、用地取得後のストーリーを構築します。ゼロから生み出す仕事なので、どのような建物にするか、どのようなテナントを入れるかなど、自由に自分の考えるシナリオで案件を進められるのが醍醐味です。
伊藤
不動産の事業性は用地取得で8割決まると言っても過言ではありません。数十億円という投資判断を自分が行い、社内外を巻き込んで成約する仕事はダイナミックで、自分が取得した土地に建物が竣工したとき、大きなやりがいを感じますね。城戸君にはまずは自分で考えてみろ、やってみろと一定の仕事を任せて育てる姿勢で臨みました。
城戸
忘れもしないのがある商業施設用地の案件。伊藤さんに密にコミュニケーションを取ってもらい、常に方向性の確認や業務の手伝いをしていただきました。僕のことを理解して業務を差配していただき、さらに一任いただいたことで強い責任感を持って業務に取り組むことができました。着実な成長を実感した案件でしたね。
阿部
私と高橋さんは、東京スクエアガーデンや大手町タワー商業部分「OOTEMORI」など、オフィスビルの管理運営を担当しています。ビルの価値向上の取り組みであるプロパティマネジメントと呼ばれる業務。入居する企業様とのリレーション構築や、賑わいを創出するイベントの企画などを行っていますが、伊藤さんと同じく、任せる、挑戦させることを意識して高橋さんと接していました。
高橋
毎日が小さな挑戦の連続でした。私たちは物件の収益を上げるのがミッションですが、そのためには入居者の満足度や物件の価値を高めなければなりません。物件の付加価値向上を目指し、さまざまな取り組みに挑戦してきました。
阿部
最近もメディアに取り上げられるなど、反響の大きかった取り組みがあったね。
高橋
毎年の風物詩になっているイルミネーションですね。今年はSDGsを意識しオーナメントにリサイクル資材を利用。メディアで取り上げられたことで、ビルだけでなくエリア価値の向上にも寄与できたと思っています。
前川
私は、今は異動しましたが、牧野さんが入社時は市場・政策調査部に所属していました。不動産を取り巻くマーケット情報や、同業他社の動向の調査・収集を中心に、不動産鑑定の知識を活かして現場部署からの相談に対するコンサル業務や社内研修なども担当していました。「見るより慣れろ」が私の指導方針。牧野さんは入社1年目で大抜擢といえる役割を担ったよね。
牧野
はい。社内の投資判断に関わる重要業務のメイン担当を任せてもらいました。当初は不安でいっぱいでしたが、前川さんをはじめ先輩方が支えてくれたので、「とりあえずやってみよう」という気持ちになれましたね。プレッシャーもありましたが、それに打ち勝つことで成長できたと感じています。
CROSS TALK
QUESTION 03
若手をカバーし、フォローする だから主体的に発信し、果敢に挑戦できる
若手をカバーし、フォローする だから主体的に発信し、 果敢に挑戦できる
前川
牧野さんの大抜擢もそうですが、みんな入社1年目から責任ある仕事を任され、最前線で業務に取り組んでいますよね。これは昔からの東京建物の文化ですが、その背景には何があると思いますか?
伊藤
風通しの良さがあるからじゃないかな。若い社員でも積極的に発言する機会があるから、結果として若手発信の意見がカタチになり、また若手に任せてみようという空気が生まれる。
阿部
伊藤さんが言うように、「若手に任せてみよう」と考える人が当社には多いです。なぜなら、上司が熱意ややる気を汲み取ってくれるからだと思います。たとえ経験値がなくても「この子ならできる、この子を育てたい」と思える人には任せたいという気持ちになるのだと思いますね。
前川
同感です。それに失敗も含めて実践で学んだ方が、早く成長できる。仕事における実践は、責任と裁量を持って取り組むことですから。必然的に仕事を任せることになるわけですね。
高橋
ただ、もう1つ感じるのは、決して任せっきりではないということ。以前、物件の販促施策を打つ際に、金銭面で取引先とトラブルになったことがあります。私の責任で落着させねばならなかったですが、阿部さんからのご指導とフォローがあって無事にトラブルを解消できました。
城戸
その点は僕も同様ですね。失敗してしまった時も、伊藤さんの的確で迅速なフォローがあったので、伸び伸びと思いっきり業務に取り組むことができました。
牧野
カウンセラーの前川さんだけでなく、周囲の先輩・上司がいつも見守ってくれている感覚がありました。今でもそれは変わらないですね。
前川
牧野さんには、「自分で考えられる人」になってほしいと思っていて。仕事をやらされている感覚では成長できませんから。「あなたならどう考える?どう進める?」というように、当事者意識を養うことを大切に指導しています。
伊藤
そうそう、自分が強く言うとそれが正解になってしまう。だから、後輩が主体的に発言できる・自由に泳げる環境をつくることは、今でも大事にしています。
阿部
デベロッパーには「傾聴力」が必要だとよく言われますが、「傾聴」は最初のステップとして当然であって、重要なことは決断して物事を前に進める力だと思う。優柔不断が最もプロジェクトを停滞させますから。だから後輩には、できるだけ決断を委ねることで成長を後押ししています。
城戸
阿部さんが先輩だと、結構プレッシャー大きそうですね(笑)。
伊藤
城戸君のような若手には、良い意味で「不動産屋さん」になってほしくない。かつては、良い場所に土地を持てば勝てる業界でしたが、時代の変化とともに、「良い場所の定義」が立地から建物・空間に変わってきている。だから不動産という枠組みにとらわれず、さまざまな業界に目を向けて、良い空間を作れる人材になってほしいね。僕自身も、そうありたいと思っています。
CROSS TALK
QUESTION 04
夢がある、挑戦したいことがある なりたい姿があるから、成長に終わりはない
夢がある、挑戦したいことがある なりたい姿があるから、 成長に終わりはない
阿部
みんなは、将来どんな先輩になりたいと思っていますか?
高橋
「こういう先輩になりたい」と思ってもらえる先輩ですね。そのため、最近は業務に自分の色を出すことを心掛けています。自分の色を出すには社内外の関係者を巻き込んで、自分の考えを実行していく必要があります。実は考えを実行に移すのは苦手。この壁をクリアすることに挑戦していきたいですね。
牧野
私は後輩が困っていたらそれを察することができる先輩になりたいです。新人は、何度も質問することに気後れしてしまうこともあると思います。そこでそっと手を差し伸べることで、より早い成長を促せるような先輩になりたいですね。
城戸
僕は実力を備えることはもちろん、尊敬されるような先輩になりたいです。そのために「for the team」を意識しています。自分の仕事が完了していたらいいのではなく、他の人からの相談や質問にも丁寧にスピーディに回答することで、周囲から信頼や尊敬を勝ち得ていきたいです。
伊藤
城戸君は、これからどんなことに挑戦したい?
城戸
社会的意義の大きな仕事ですね。たくさんの人に大きな影響を与えるような開発に携わりたいです。従来の不動産の概念を覆すような、先進的でインパクトのある魅力ある開発を手掛けることを目指します。
伊藤
城戸君の言ったことにも関連するかもしれないけど、僕は新規事業を立ち上げることが目標。ビジネスの本質を理解できる人材に成長して、将来は、不動産×〇〇というような新しい事業の立ち上げに挑戦したいと思っています。
前川
私は今「Brillia」の事業推進を担当していますが、近い将来の目標としては、お客様が本当に望む物件をつくれるようにうなりたいですね。潜在的なニーズは何かを深く考え、それらを満たせる物件をつくっていきたい。牧野さんはどんなキャリアを描いていますか?
牧野
せっかく珍しい部署に配属されたので、そこで得た知識(特に不動産鑑定の知識)を活かすことのできるキャリアを歩みたいです。そのためにもまずは、難関ではありますが、不動産鑑定士の資格取得に挑戦します。
高橋
私は今の仕事に即して言えば、担当テナントや取引先、あるいは社内のメンバーから「高橋だから相談してみよう」「高橋が担当でよかった」と思っていただけるような人材に成長することが目標です。阿部さんが目指すものは?
阿部
人の心に刺さる伝え方で東京建物への共感者を増やし、当社の知名度をさらに高めていきたいですね。不動産はもはやハコをつくるだけでは勝ち残れない。建物開発やまちづくりなどを通して、「愛着」「誇り」「思い出」など、さまざまな記憶と結びつく存在を生み出す必要があります。そのためにも、人の気持ちを動かし、人を奮い立たせる、そんな仕事に取り組んでいきたいと思います。
※記事内容および社員の所属は取材当時のもの、在籍時の部署名称となります。