
新中期経営計画期間の安定的な成長を経て、
「次世代デベロッパーへ」の実現を目指す
代表取締役 社長執行役員
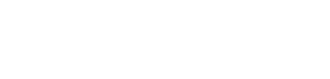
2025年1月に当社社長に就任し、それとともに新たなグループ中期経営計画(以下、新中計)をスタートさせました。また、新中計の策定にあわせて、2020年に策定した長期ビジョン「次世代デベロッパーへ」の目標年度を見直しました。2020年の策定当初は当社が推進している複数の大規模再開発プロジェクトの竣工時期を見据えて、目標年度を「2030年頃」としていましたが、前中期経営計画期間において今後の「利益成長の基盤」を固めることができ、社内外に向けて長期ビジョン実現への意志を表明したいと考え、「2030年」と明確な年度に変更しました。長期ビジョンの基本的な考え方、目指す姿に変更はありませんが、新中計の着実な推進に加え、長期ビジョンで掲げる目標の必達を目指し、全役職員一丸となって邁進することが社長として最大のミッションであると捉えています。社長就任は身が引き締まるほどの重責ですが、これを全うしたいと心に誓っています。
はじめに
私が当社の扉を叩いたのは今から38年前、これまでに社会・経済の大きなうねりを経験しつつ、社内の様々な部門の業務に携わりました。激動の社会の中で変革に携わる経験は、ビジネスパーソンとしての私自身の人格形成にも大きく役立ったと考えています。
日本がバブル崩壊を迎えた1990年代初頭は住宅開発業務に従事していましたが、マーケットの急速な崩壊に直面し、担当物件の大幅な事業方針の変更対応に奔走しました。その後、人事部での経験を経て、2000年代には当社が業界に先駆けて取り組みを進めていた「不動産証券化業務」に携わり、J-REIT市場の黎明期において、日本プライムリアルティ投資法人(JPR)を立ち上げ、その運営業務に従事しました。
2007年に帰任したものの、2009年からは前年のリーマンショックにより財務内容の悪化したJPRの再生業務のために資産運用会社に再出向し、不動産金融を通じて資本市場のダイナミズムに触れ、金融機関や投資家と直接向き合い、信頼を構築していくことの重要さを痛感しました。2012年からは当社経営企画部長として、前年に大幅な赤字を計上した当社グループ全体の再生業務・構造改革・組織再編を主導。また、2017年からCFOとして、財務戦略の推進、前中期経営計画(2020~2024年)(以下、前中計)の策定なども担ったことで、利益成長と財務規律の両立の重要性をあらためて認識することができました。直近2021年からはビル事業本部長として、新型コロナウイルス感染拡大、地政学リスクの顕在化、オフィス・ホテルなどの市場環境の急激な悪化など、非常に先行きが見通しづらい中、大規模再開発事業・資産回転型事業を中心に当社の成長の礎を築くことに注力しました。
これからはCEOという立場になりますが、度重なる困難な時期を乗り越え、会社とともに成長してきた経験を存分に活かし、ステークホルダーの皆様との様々なコミュニケーションを通じて、更なる企業価値向上に真摯に取り組んでまいります。
東京建物らしさの源流
129年前、創業者の安田善次郎が志したのは「不動産取引の近代化」と「市街地開発の推進」でした。「建物があってこそ、不動産は価値を生むもの」という信念が当社グループの原点であり、その信念のもと、「お客様第一」の精神と、時代の流れを先んじて捉える進取の精神が今なお息づいています。また、当社グループは、1896年の創業以来、「3つの強み」を醸成してきたと考えています。
1つ目は、地域の新たな魅力を引き出す「不易流行」のまちづくりです。伝統や文化を重んじながら、地域に新たな価値をもたらすことができる力を持つことは、当社グループの大きな強みの一つです。東京の八重洲、日本橋、京橋界隈は、江戸時代には商人や職人が集う、町人文化が花開くまちとして知られていました。今はそれぞれの頭文字を取って「YNK(インク)エリア」と呼んでいますが、当社グループはこれまでこの地域において、「想いをつなぎ、新しきを育むまち」をテーマに掲げ、まさに「不易流行」のまちづくりに取り組んできました。江戸の町人文化やDNAを受け継ぎながら、国際都市である東京の中心部にふさわしい、多様性に富んだ、また人々のウェルビーイングを向上させるまちづくりを目指しています。2026年の開業を目指す「TOFROM YAESU」は、まさにその象徴と言えます。
2つ目は、革新に挑み、未来を切り拓く「進取の精神」です。創業者の精神とDNAが約130年の時を経て育まれ、継承されてきたものと考えています。当社では従業員の自立や主体性が重視されており、日本初のSPC法を活用した不動産証券化の実現、中央官庁初のPFI事業「霞が関コモンゲート」、都市と自然の再生を両立した「大手町タワー」などは、社会や業界に先駆けた取り組みであったと自負しています。常に新しいことにチャレンジする姿勢が貫かれてきたこと、言い換えれば、時代の流れをいち早く察知し、行動する企業文化が根づいていることは、当社グループの大きな強みと言えます。
そして3つ目は、時代の変化を捉えた柔軟かつ俊敏な適応力です。これは、経営と現場の距離が近く、現場のアイデアが経営に反映されやすい社風により形成された強みだと考えています。フラットな組織によってコミュニケーションが円滑化し、変化を受容する柔軟性が組織に備わり、迅速な意思決定を実現させています。当社グループはこれらの柔軟さと俊敏さを備えた組織体系・企業風土によって、前中計期間中には、従来のオフィス・住宅が中心の事業ポートフォリオから、商業施設、ホテル、物流施設など、環境変化に応じてアセットタイプを多様化し、短期間で業容を拡大できたものと考えています。

「次世代デベロッパーへ」に込めた想い
変化の著しい時代、世界情勢を含め不確実性が急速に高まる時代にあって、「社会課題の解決」と「企業としての成長」を従来とは違うレベルで両立することのできる企業だけが持続的な成長を実現することができると考えています。この考えを背景に、2020年に、長期ビジョンとして「次世代デベロッパーへ」を打ち出しました。私をはじめ新経営陣も、これまでの経営陣が進めてきた考え方を踏襲しつつ、引き続き長期ビジョンの達成を目指し、突き進んでいく覚悟です。
長期ビジョンにおける「デベロッパー」という言葉には、私たちの強い想いが込められています。単にビルや住宅などの建物を開発することにとどまらず、サービスを含めて人が「住まう」「働く」「憩う」場をつくり、長期的な視座からまちの機能を高め、文化を生み出す支えとなることで、当社グループ自体の収益も積み上げていきたいと考えています。そのために、経営陣はもとより、不動産開発に関わる社員、販売や運営・管理に携わる社員、すべてのグループ社員が共創しながらシナジーを発揮し、まちや社会を「デベロップ」して付加価値を創出していく、一人ひとりがそのような意識を持つ企業グループでありたいと思います。
2021年6月、私たちは長期ビジョンの実現に向けて、事業を通じて実現する「社会との共有価値」の創出を意識し、「社会価値創出」と「価値創造基盤」の観点から重要課題とするマテリアリティを特定しました。事業活動により「社会価値創出」として掲げる重要課題に取り組むことで、「『場の価値』と『体験価値』の創出」、さらには「地球環境との共生」という共有価値を生み出していきます。また、マテリアリティの土台となる「価値創造基盤」については「価値を創造する人材」と「サステナビリティ経営の実現」という共有価値を生み出します。一例として、当社が創業以来、本拠を構えてきたYNKエリアでの取り組みは、社会との共有価値を創出している事業だと認識しています。地域住民や地権者の方々と協力して行うまちづくりは国際都市東京の競争力強化に貢献するほか、先にご紹介した「TOFROM YAESU」においては人々の「ウェルビーイング」の向上を企図しており、脱炭素社会・循環型社会の推進にも取り組んでいます。
2030年を見据えた長期ビジョンの実現には、財務と非財務の両輪を意識したバランスの良いマネジメントが必要であると考えています。事業活動を通じてマテリアリティとして特定した重要課題に取り組むことで、社会に与える正の影響(機会)を最大化しつつ、負の影響、つまりリスクの最小化を図り、企業としての成長を続けながら、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
また、当社では中期経営計画を長期ビジョン達成のためのマイルストーンとして位置付けており、新中計は長期ビジョンの実現・達成を念頭に、「成長の礎」を集中的に構築するため、3年間の計画としました。さらにその先の話をすれば、次の中計では、長期ビジョンで掲げる目標達成に向けた実績と進捗状況を精査したうえで、長期ビジョンの実現に向けた詳細なアクションプランを盛り込むこととなるでしょう。三段跳びで言えば、前中計で踏み出した「ホップ」、それに続けて現在取り組む新中計期間の「ステップ」、さらにその先の「ジャンプ」をもって、長期ビジョンの実現に向けた価値創造ストーリーを確実に実現させたいと考えています。
新中期経営計画を通じた「成長の礎」の構築
前中計の5年間は、まさに波乱に富んだ経営環境が続きました。コロナ禍が続く中で、お客様の価値観・行動様式やマーケット環境は大きく変わり、ロシア・ウクライナ戦争や中東情勢の悪化など、地政学リスクの高まり・顕在化は今なお世界中の人々に不安をもたらしています。国内においては、異次元の金融緩和政策の転換があり、金利のある世界が復活しています。また、インフレや人手不足などを受けた建築費の急騰は足元での大きな課題となっており、加えて、米国による関税政策がどの程度の影響を及ぼすのか、当社グループにおいても各事業の今後の見通しについては注視しなければならないと考えています。
一方で、私たちが身を置く不動産市場に目を移すと、収益不動産の売買市場は引き続き好調に推移していますし、分譲住宅市場においては、利便性の高い都市部の物件を中心に、パワーカップルやスーパーパワーファミリーと呼ばれる高収入の共稼ぎ世帯や富裕層などの不動産購買ニーズには底堅いものがあり、価格の上昇傾向が継続しています。また、コロナ禍で一時期悪化したオフィス賃貸市場についても、国内経済全体の回復や人材採用を投資と捉える企業ニーズの増加などを背景に稼働率は高水準で推移し、今後の賃料収入の増加に対する手応えも日に日に高まっています。

当社グループはこれまで、事業環境の不確実性の高まりや変化のスピードの加速が見られる中でも、持ち前の高い商品企画力・開発力を原動力として、良質な不動産ストックを確実に積み上げてきました。前中計期間では、この取り組みにより低金利をはじめとした良好なマーケットを捉え、分譲マンション事業・投資家向け物件売却事業が好調に推移した結果、利益目標、資本効率、財務指針のすべてのKPI目標を達成することができました。
前述したとおり、2025年を初年度とする3カ年の新中計は、長期ビジョン達成に向けた三段跳びの「ステップ」に相当する位置付けです。この3年間で成長の礎を集中的に構築すべく、新中計の基本方針を「強靭かつしなやかな事業ポートフォリオの構築により、成長加速・資本効率向上を実現する」と定めました。この方針に基づき、強固な長期安定収益を基盤に、資本効率の高い資産回転型事業を時機を捉えてしなやかに加速・拡大していきます。回収した資金は、資産回転型事業とともに大規模再開発などの事業へ活用し、安定収益基盤の一層の強靭化を図ります。また、サービス事業の力強い拡大を図ることで、バランスの良い事業ポートフォリオを構築し、持続的な成長を実現できる事業構造の確立を目指していきたいと思います。
そしてこの基本方針のもと、次に挙げる具体的なアクションに取り組むことで、新中計期間中における成長加速・資本効率向上を確たるものとしていきたいと考えています。
(1) 資産回転型事業の加速・拡大
投資家向け売却用物件については、前中計期間を通じて物流施設を中心に売却益のストックを大きく積み上げることができたと捉えています。新中計では、これらの売却・取得サイクルをさらに加速させていくとともに、海外事業の拡大や分譲マンション事業の一層の強化を図ることで、資産回転型事業を加速・拡大させます。
(2) 安定収益基盤の強靭化
長期ビジョンでは、利益成長の基本方針として「安定的な賃貸利益を基盤としながら、資本効率を意識したバランスの良い利益構成を目指す」ことを掲げています。その基盤を構築するため、現在推進する大規模再開発プロジェクトを着実に進めつつ、ややオフィス偏重となっている長期保有目的の賃貸資産ポートフォリオについては見直しを図ります。具体的には、収益の安定性やリスク耐性の強化、効率性の向上を意識して、ポートフォリオの多様化を進めたいと考えています。
(3) 規律あるバランスシートコントロール
前中計では、バランスシートの強化に向けて政策保有株式の売却を進めました。これについては新中計期間においても継続していく考えですが、これに加え、固定資産の戦略的な売却によって含み益を実現益として顕在化し、資金回収・投資のサイクルを加速させたい考えです。
また、新中計においては成長戦略に加えて、「成長を支える経営インフラの高度化」を掲げ、「サステナビリティ(環境・社会・ガバナンス)」「人的資本」「DX」を成長の土台として位置付けています。
サステナビリティに関しては、「地球環境との共生」というキーワードをマテリアリティの枠組みで掲げています。最近は「リジェネレーション」という言葉を耳にするようになりましたが、例えば環境負荷を低減し、今の環境を維持していこうという従来の考え方からさらに一歩進み、いかに再生して価値を高めるかというステージ、時代に突入しつつあります。長期ビジョンとして掲げる「次世代デベロッパーへ」も、こうした発想を持って取り組んでいくことが重要ではないかと考えています。
人的資本の強化に向けては、人材ポートフォリオの構築、多様な人材の活躍を両輪として取り組んでいきます。人材ポートフォリオの構築では、新卒・キャリア・専門人材の採用拡充や、資産回転型事業といった成長・注力分野への人材シフトを進めるなど、多様な人材の採用・育成、全体最適な配置を強く意識して進めます。多様な人材の活躍では、女性やグローバル人材など多様な「強い個」の活躍と、「チーム力」の最大発揮に力を注ぎます。また、当社の強みの根底には、凡事徹底や内発的行動を重視する人間力のある社員を育てる企業風土・文化があります。昨今の事業拡大に伴い、良質な企業風土や文化、組織のDNAが希薄化しないよう、様々な取り組みを進めてまいります。
「DX」については、当社自体の経営の高度化を実現する手段として活用を加速化させていくことに加え、社会やお客様のニーズの変化を捉え、課題の解決のためにデジタル技術を活用し、データドリブンな対応を図っていくことが重要なカギであると認識しています。また、DXに取り組むことにより、業務効率化が進み、注力分野へ人的リソースを集中させられるといったように、経営インフラの高度化に掲げる3つの分野はいずれも連動していくと考えています。新中計の期間にとどまることなく、長期ビジョンのターゲットイヤーである2030年やその先の将来を見据えて、広い視野を持ち、時代の変化を捉えた柔軟かつ俊敏な適応力によって、経営インフラの高度化に積極的に取り組んでいきます。
ステークホルダーの皆様へ
「企業は人なり」「人材こそ最大の財産」という言葉をよく耳にします。私自身、人事部門に身を置いた経験から、人材の持つ無限の可能性・重要性を実感しています。1996年からの4年間、採用や研修、人事制度の立案などに携わっており、その頃に採用した社員たちが今回の私の社長就任を祝ってくれました。彼らはアジア通貨危機や日本の危機と重なる時期に入社しており、入社後もリーマンショックや東日本大震災、コロナ禍など苦しい思いを経験してきていますが、今やそれぞれが会社の中核を担う人材となっていることに感慨深いものがありました。私は、役職員一人ひとりが自らの仕事に誇りを持ち、持てる力を最大限に発揮する風土を醸成すること、人材の力を結集して企業としての持続的な成長と価値向上につなげることが、経営者としての最も重要なミッションであると信じています。
当社グループは、グループ理念として「信頼を未来へ」を掲げ、世紀を超えた信頼を誇りとし、企業の発展と豊かな社会づくりに挑戦することを宣言しています。また、前述のとおり、2030年を目標年度とした長期ビジョン「次世代デベロッパーへ」を掲げ、事業を通じて「社会課題の解決」と「企業としての成長」をより高い次元で両立することで、すべてのステークホルダーにとっての「いい会社」を目指すことを表明しています。こうしたグループ理念や長期ビジョンの実現を目指して、2025年を初年度とする3カ年の新中計を策定しましたが、当社グループの企業価値に対する資本市場からの評価という点では、現状のPERやPBRの水準から、当社の中長期的・持続的な成長ストーリーに対して十分な理解が得られていないと感じています。新中計では、資本効率重視の姿勢を鮮明に打ち出し、利益成長のための成長投資や株主還元の充実によって企業価値の向上につなげていくことを強く意識しました。私は、経営者として会社の先頭に立ち、計画を確実に実行に移していくことで、今後の成長に対する資本市場からの期待と信頼を獲得することに全力を注ぎます。
当社グループは129年続く、良質な社風と志を持つ企業集団であり、創業者の精神を受け継ぎながら、進取の精神を発揮し、これからも不動産事業を通じて新たな付加価値を提供し続けます。若返りが図られた経営陣のもと、全役職員一丸となり、すべてのステークホルダーにとっての「いい会社」を目指して邁進していきますので、今後とも当社グループへのご理解と一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
