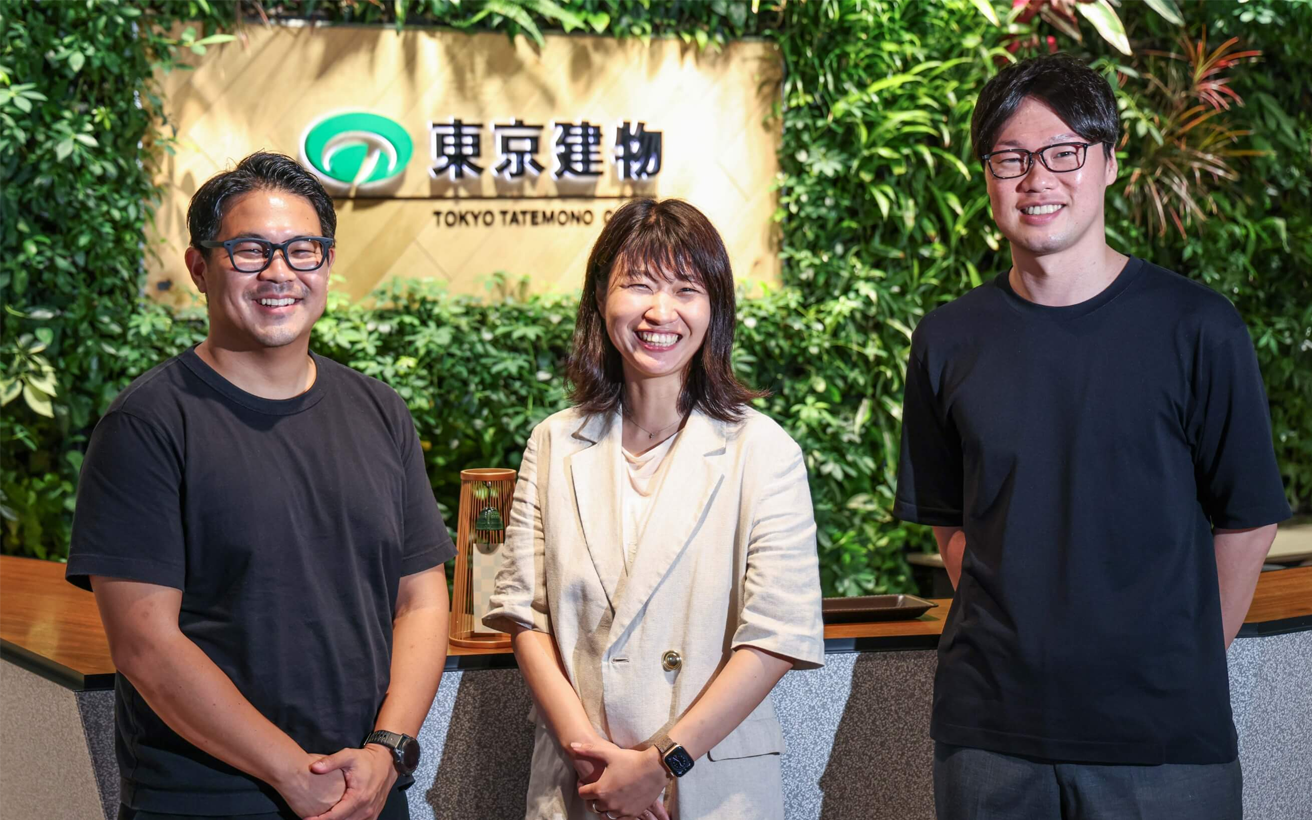社会課題の解決と企業としての成長を
より高い次元で両立させ
サステナブルな未来を切り拓く
東京建物株式会社
代表取締役社長執行役員


社会課題の解決、企業としての成長を
高次元で両立させ
サステナブルな未来を切り拓く
東京建物株式会社 代表取締役社長執行役員

当社は、1896年に安田財閥の創始者である安田善次郎が「不動産取引の近代化」と「市街地開発の推進」を使命として創業した会社です。創業以来、安田善次郎が旨とした「お客様第一」の精神と、時代の流れを先んじて捉える進取の精神を企業活動の原点としてきました。そして、不動産事業を通じて「社会課題の解決」と「企業としての成長」に取り組んできた結果、130年近く存続してきました。長期ビジョンに掲げる、次世代デベロッパーとして「社会課題の解決」と「企業としての成長」をより高い次元で両立し、すべてのステークホルダーにとっての「いい会社」を目指そう、という決意そのものが、サステナビリティに関する当社グループの考え方や、想いを表しています。
私自身、サステナビリティに対する社会の危機意識の急激な高まりを痛切に感じたのは、2011年3月11日に発生した東日本大震災の時でした。激甚化した自然災害によって凄まじい被害が生じ、サステナブルな社会への取り組みが改めて問い直されることとなりましたが、当時私は当社が出資するJ-REIT※1の資産運用会社で、当社のグループ会社である東京建物リアルティ・インベストメント・マネジメントに出向していました※2。J-REITは投資対象が不動産の集合体であるため、市場が誕生した当初から積極的に情報開示を行い、透明性を確保することで資本市場や個人を含めた投資家からの要請に応えるよう努めていました。さらに震災による対象不動産への影響に関する情報は国内外の投資家にとって非常に重要な情報となりますが、東日本大震災のような有事の際の対応は過去に同様の事例があるわけではなく、開示情報の適正性をいかに確保するかが課題となりました。そこで、震災直後は情報収集や情報開示の対応が困難な状況ではありましたが、対象不動産の運営管理を受託していた当社とも連携して可能な限り情報を収集し、スピードを重視して震災翌日の夜中の2~3時には震災による物的な影響の程度を日本語と英語の両方で情報開示をしました。後日、この情報開示は投資家等から高い評価を受けることとなりましたが、社会環境の変化に応じた対応や有事の際の対応はもちろん、常に透明性をもって情報開示をしていくことが重要だと考えます。
当社は、創業来「不動産取引の近代化」と「市街地開発の推進」を使命とし、不動産事業を通じて「社会価値の創出」に取り組んで参りましたが、この姿勢を貫いてきたからこそ約130年という長い年月にわたり存続してきたのだと考えています。このような当社の姿勢を、今後も大事にしていきたいと思います。
-
※1日本プライムリアルティ投資法人。
-
※2出向期間は2009年から2015年。出向当時の会社名は「東京リアルティ・インベストメント・マネジメント」。
2030年の長期ビジョン実現とサステナビリティの関係性
当社グループでは、2020年に、「2030年頃」を目標時期とする長期ビジョン「次世代デベロッパーへ」を公表しました。事業を通じて「社会課題の解決」と「企業としての成長」をより高い次元で両立することで、すべてのステークホルダーにとっての「いい会社」となることを目指しております。今般、目標時期をより明確にするため、「2030年頃」を「2030年」に変更しました。
長期ビジョンの達成に向けては、2021年に、事業を通じて実現する社会との共有価値を意識し、取り組むべき重要課題として14のマテリアリティを特定しています。サステナビリティの観点からは、「『場の価値』と『体験価値』の創出」や「地球環境との共生」という社会価値創出に分類される「安全・安心な社会への貢献」や「顧客・社会の多様なニーズの実現」などを特に意識しています。
長期ビジョンの目標時期である2030年に向けては、中期経営計画をマイルストーンと位置付けており、 2020年から2024年の中期経営計画(前中計)をホップ、2025年から2027年の中期経営計画(現中計)をステップという位置付けとしました。
前中計ではESG経営の高度化を掲げていましたが、そのベンチマークとしていたESG格付機関による評価やインデックスへの組み入れが進んだことから、ESG経営の高度化について一定の評価が得られたものと考えています。ただし、ESG経営の高度化も一つの目的ではありますが、それを通じて長期ビジョンに掲げる「社会課題の解決」と「企業としての成長」をより高い次元で両立することこそが重要です。その目的を果たすためのベースとして存在するのが、現中計に掲げる「経営インフラの高度化」です。現中計では、「サステナビリティ(環境・社会・ガバナンス)」を、相互に高め合う関係にある「人的資本」や「DX」とともに、経営インフラの高度化を推進するうえでの基盤ということで改めて位置付けました。長期ビジョンの達成に向けたステップ(成長)期間である現中計において、サステナビリティが経営インフラの重要な要素であることを明確に定義付けることで、全員で長期ビジョンの実現に向かって取り組みを推進・加速していこうと考えています。
不動産事業では開発に長い期間を要し、具体的な取り組みが効果となって発揮されるまでに時間がかかる場合が多く、長期ビジョンに掲げる2030年の目標を達成するためには、現中計の3年間が大事な期間となります。2030年を目標時期とする環境関連の目標も同じで、2027年までの現中計の期間を目標達成に向けたマイルストーンとしてモニタリングし、最終の2028年からの期間につなげていくことが重要となります。

エリアを越えて他社と協力関係を築き、東京をサステナビリティで世界に先駆ける都市に
当社は、1896年に創業して以来、重点エリアとする八重洲・日本橋・京橋(YNK)エリアに拠点を構えてきました。現在当社では、八重洲通りに面した旧本社の敷地を含む大規模再開発「八重洲プロジェクト」を「TOFROM YAESU」と命名して推進しています。このTOFROM YAESUを起点とし、八重洲エリアにおけるもう一つの大規模再開発「呉服橋プロジェクト」などを含めて、これからもYNKエリアの活性化や価値向上、にぎわい創出に取り組んでいきます。こうした取り組みを通じて、いかにYNKエリアの将来的な付加価値を高められるかが、当社の存在意義の一つと言ってよいでしょう。
ただ、YNKエリアの将来的な付加価値を高める取り組みは、当社だけで実現できるものではなく、地元の地権者、拠点を構える企業等の皆様や、このエリアで取り組みを展開する産官学の様々なプレーヤーと連携していくことが重要です。例えば、エリア全体の環境性能を高める検討においては、TOFROM YAESUや呉服橋プロジェクトでコージェネレーションシステム(CGS)という高効率な設備システムを導入予定であり、CGS廃熱直接利用やCGS廃熱利用冷凍機および蓄熱槽を組み合わせた高効率な地域冷暖房(DHC)プラントなどを整備するとともに、既存のDHCプラントとの間でエネルギーを融通し合うことで、エリア全体でのエネルギーの効率的利用を図っていきます。また、YNKエリア内の建物の温湿度などの環境データや、ワーカーや利用者の人流データを一元化し、活用することでエネルギー効率の最適化に結びつけ、環境負荷の低減につなげるといったスマート化の取り組みも検討しています。民間のデータだけではなく、行政機関とも連携して公共インフラに関するデータも収集し活用することで、より効率的なスマート化が実現できると考えています。
加えて、TOFROM YAESUにおいては、ワーカーのウェルビーイング向上につながる多様な取り組みを推進予定ですが、それだけではなく、このエリアの他の企業とも連携し、YNKエリアをウォーカブルな街にしていきたいと考えています。たくさんの人々が集まり、街を歩くことで自然と楽しくなってウェルビーイングになれるような、そのような街を目指しています。さらにはYNKエリアだけではなく、東京駅を挟んだ反対側の丸の内エリアで様々な取り組みを展開する多様な企業と連携を図り、日本の中心である東京駅周辺エリアの価値を一層高めることができれば理想的ではないかと考えます。こうした取り組みが、東京という街の魅力をさらに向上させ、国際都市としての競争力を強化することになると考えています。
サステナブル ディベロップメントの実現を目指して
サステナブル ディベロップメント ゴールズ(SDGs)、「持続可能な開発目標」は、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標として広く世の中に浸透しており、当社の長期ビジョンにおいても「様々な社会課題の解決」として「SDGsへの貢献」を掲げ、また、長期ビジョン実現に向けて特定したマテリアリティにおいては、事業を通じて実現する社会との共有価値である「地球環境との共生」を意識して、「脱炭素社会の推進」「循環型社会の推進」を重要課題として特定しています。
ここで、「SDGs」として使われている「サステナブル ディベロップメント」は、1987年に国連の「環境と開発に関する世界委員会」の中で定義付けられており、「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、今日の世代のニーズを満たすような開発」を意味しており、環境と開発の共存を目指した概念とされています。
私たちは、これからの開発や建物の管理、運営において、このサステナブル ディベロップメントを実現するべく、様々な取り組みを進めています。
建物は時間の経過とともにハード面の劣化が進行するものですが、例えばオフィスビルであれば働いている人に働きやすいと感じてもらうこと、マンションであれば住んでいる人が住み心地が良いと感じてもらうことなどを通じて、資産価値を低下させず、むしろ向上させることができるのではないかと考えています。
例えば、当社が分譲したマンションにおいては、分譲後に廃食油や衣類・雑貨などの回収や、ごみ置き場の環境改善などの取り組みを始めていて、マンションの購入者から大変高い評価をいただいています。通常、分譲後のマンションの共用部分については、管理組合が運営を担うこととなりますが、当社グループは、マンションの価値を維持・向上させる様々な取り組みを管理組合に積極的に提案することで、ソフト面から資産価値を維持・向上することにチャレンジしています。
また、YNKエリアにおけるスマート化の取り組みを前述しましたが、そもそもスマート化は最新のデジタル技術の活用によって様々なデータを収集し、このデータを一元的に管理することでオペレーションの最適化を目指すものであり、データドリブンな取り組みと言うことができます。スマート化が進むと、データがますます蓄積されることになり、これを最大限活用することによって、効率化、高度化を図り、持続的に資産価値を維持・向上することも可能になるでしょう。
ステークホルダーの皆様へ
これまでの企業経営では、株主還元や財務的リターンのみを重視する「株主資本主義」が中心とされていましたが、現在は顧客や地域社会、取引先や社員などあらゆるステークホルダーへの貢献や価値共創が求められる「マルチステークホルダー資本主義」へと転換が進んでいるものと思います。
当社グループは、こうした状況も踏まえ、ステークホルダーとの強固な関係を築いてすべてのステークホルダーにとっての「いい会社」を目指してまいります。そして、冒頭来触れてきたように、事業を通じた「社会課題の解決」と「企業としての成長」をより高い次元で両立する「次世代デベロッパーへ」の変革を強力に推し進めていきます。サステナビリティに関連した様々な打ち手を講じ、それらについて適時適切な情報開示をするとともに、ステークホルダーの皆様と積極的な対話を行い、皆様からの意見にしっかりと耳を傾けることで、グループ一丸となって、社会価値の創出と、持続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。今後とも当社グループへのご理解と一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。